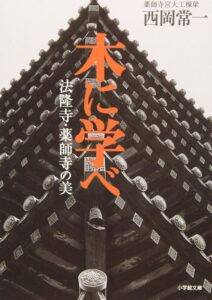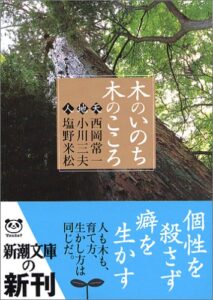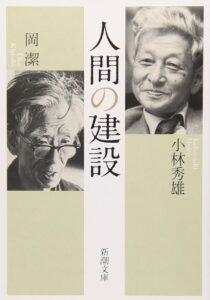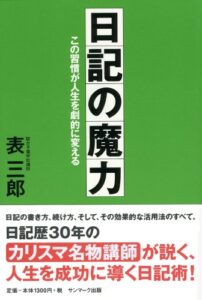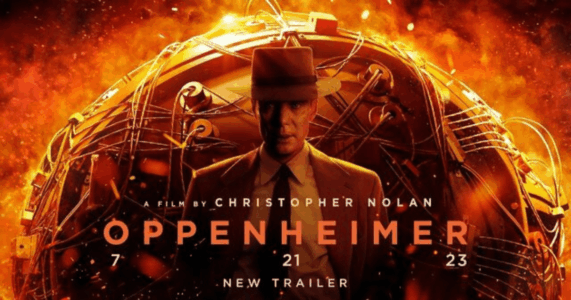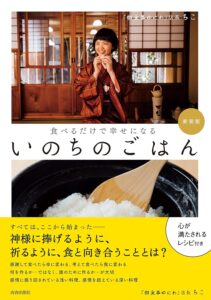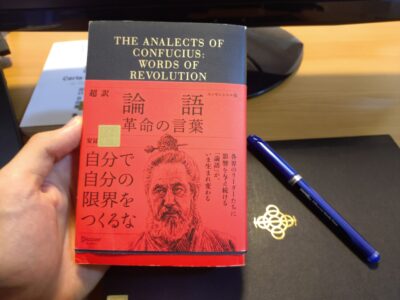苦手なことほど、上手になる。
過去を振り返ってみると、
苦手に思ってたことほど、
のちのち上手になってるなぁ…
というのを思います。
カフェ修行がはじまったときも、
ミルクフォームが一番意味わからなかった。
どうやれば上手くなるのか
トント検討がつかぬ。苦手だ…。
でも、気づいたら、
いま、一番褒められるのは、
ミルクフォームだったりする。
アメフトをやってたときも、
ムーブメントといって、
体の動かし方のトレーニングが
チームの誰よりも、ぎこちなかったのを覚えてる。
でも、社会人リーグでやってるときに
一番自信があり、一番通用してたのは、
ムーブメントだったりする。
不思議。
今日、岡潔(おかきよし)の
著書「春宵十話(しゅんようじゅうわ)」
を読んでいて、このような文がありました。
「いまの学生で目につくことは、
非常におごりたかぶっている
ということである。
もう少し頭が低くならなければ
人のいうことはわかるまいと思う。
謙虚でなければ
自分より高い水準のものは
決してわからない。
せいぜい同じ水準か、
多分それより下のものしかわからない。
それは教育の根本原理の一つである。
だからそういう態度でいれば
必ず下に落ちてゆくもので、
まず上に行くことはない。」
なかなかに、辛辣。
自分にとって、得意だなーとか、
できてるなーって思ってることって、
ひとからの意見に耳をかせなかったり、
耳をかしても、大して受け取らなかったりする。
なんなら、
「それはちがう。これはこうでしょ」
とか、言い返したりしちゃって。
自分もプログラミングには
多少に腕に覚えがあるのもあって、
システム部の同僚や、関係者に、
「自分のこの意見は、絶対にただしい!」
と、傲慢な態度をとってしまうことがある。
もちろん、それはそれで
必要なタイミングはあるだろうけど、
それでは、
自分よりも高い感覚を受け取ることはできない。
すべてマッサラな状態で、受け取る。
そのためには「謙虚さ」、
つまりは、自分はまだまだだという自覚がいる。
できない自分を認めるからこそ、
受け取れるものがある。
思えば、苦手なものが上手になるとき、
そばには、必ず自分よりも上手なひとがいた。
いまもそう。
自分よりも上手なひとに教えてもらっている。
そして、気づいたら、
ちょっとずつ感覚がうつっている。
だから、自分が上手くなったというより、
いろいろ、受け取った感じ。
技術ややり方といっても
自分で生み出したものなんて、ひとつもない。
ただ、先輩のやってきた感覚を移しただけ。
感覚を全部、マルっと受け取る。
そこには、謙虚さが必要
(といって、謙虚になれば楽なのだが、
現実は、そうはいかない。)
ということを実感しました。
苦手なのは、ひとから教わる良い機会になる。
ひとと繋がるきっかけとなる。
そう思うと、苦手に感謝しています。
苦手よ、ありがとう。
できない自分よ、ありがとう。
それはきっと、いつかあなたを助けてくれる。
本日も、ありがとうございました!
松井